こんにちは。そら(@sora0free0)です。
今回6冊目は、北野唯我さんの「職場の人間関係に悩む全ての人へ〜天才を殺す凡人」を読んだ感想です。
本書を読んで、まず結論からいうと、世の中には3つの才能に分類されます。
「天才」「秀才」「凡人」
これは特定の誰かではなく、あなた自身の中にもいる3人です。
三者の間にはコミュニケーションの断絶があります。
凡人は天才を理解できず、排斥するよう行動を起こします。
秀才は天才に憧憬と嫉妬心を持つが、天才は秀才にそもそも関心がありません。
秀才は凡人を見下し、凡人は秀才を天才と勘違いしています。
この本で学べることは?
- なぜ、あの人は理解してくれないのか
- 職場の人間への考え方を一新できる
- どうしてあの人は、あんな言動をするんだろうか
それでは、読んだ感想も含め、まとめて共有したいと思います。
よろしくお願いします〜〜。
『天才を殺す凡人』のざっくり要約
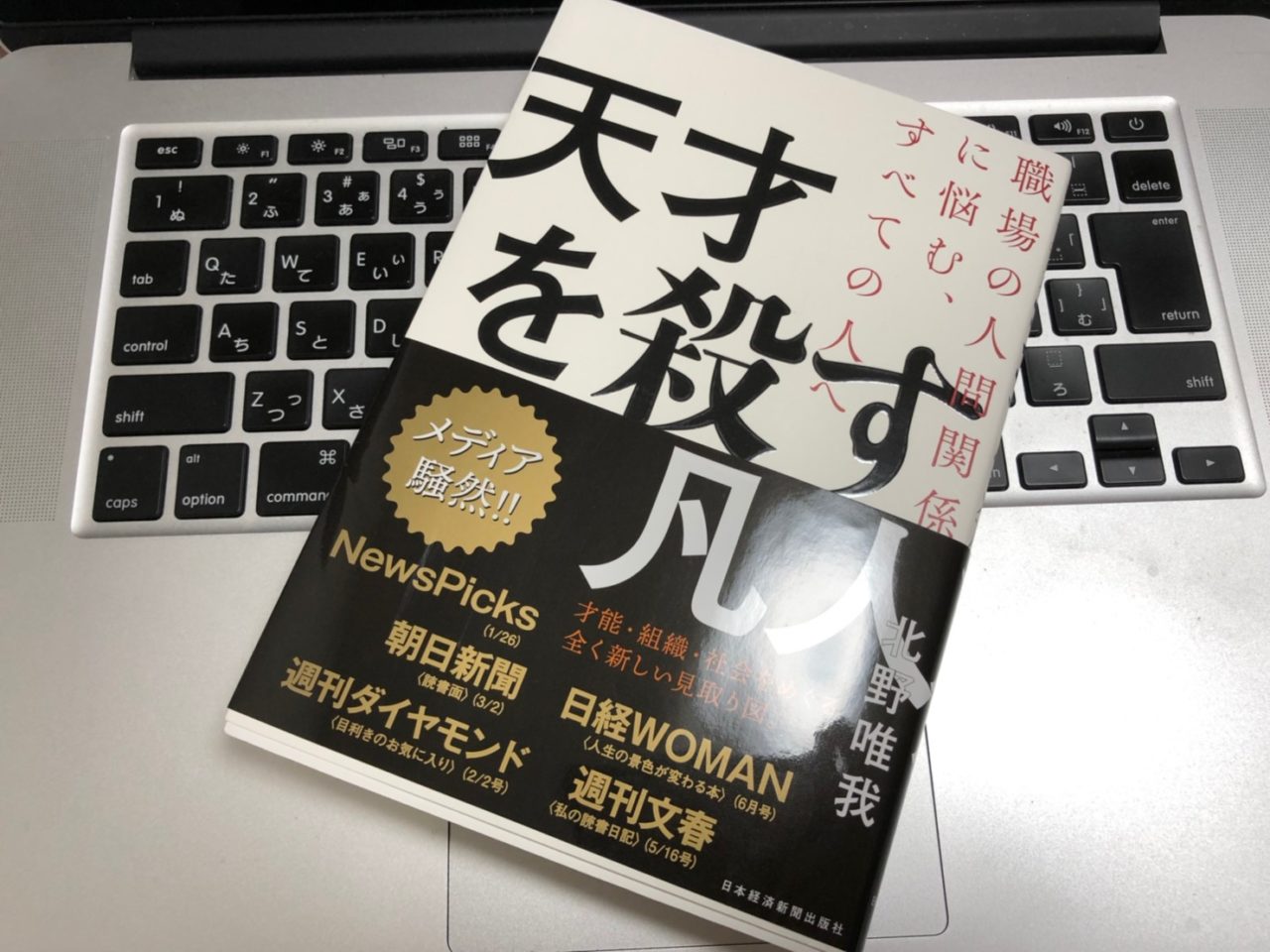
主人公の青野と忠犬ハチ公のケンとのやりとりのストーリー形式になっています。
ケンのキャラ設定は僕の中で「夢をかなえるゾウ」にそっくりで違和感があったのですが、サクサク読めるのでよかったです。
組織で、成果を出し続けるには、創造性(天才)、再現性(秀才)、共感性(凡人)の3つが上手く機能し掛け算されることが大切です。
お互いにとって必要不可欠なのに、会社という組織ではそれが活かしきれていないケースが多く見られます。
天才が潰され、凡人が能力を押し殺し力を発揮できないのか。
それは何故でしょうか。
そして、どうすればその3つの才能を活かしきれるのだろうかという流れでストーリーは進んでいきます。
本を読んで気づいたこと
僕は会社の成長ステージによって、北野さんが言っている天才、秀才、凡人の3つの要素を上手く調整することで会社は成長していくのかなと思いました。
多様な人材がいることにより、会社は成長し続けます。また逆に、それが出来なければ、会社の成長は止まり潰れてしまうかもしれません。
例えば、僕の会社では、
私の会社は「天才(創造性)=社長」がガンガン引っ張っていきました。
そのあとを担える「秀才(再現性)=執行役員クラス」がいなければ、成長スピードは減速しどんどん落ちて行きます。
さらに、「社長」と「執行役員」を上手くつなぐ役割の「凡人(共感性)=現場マネジャー」が才能を発揮することができていません。
成長スピードは鈍化するどころか、組織はぎくしゃくしてきて、成果を出すどころか社内の雰囲気は悪くなるし売上も伸びなくなってきました。
さらにその下の現場メンバーからすると上の人は会社をどのようにして行きたいのかわからず迷走しています。
とりあえず、先の見えない仕事に忙殺され比叡している状態が続いています。
僕も含めて一般の人間が、自分の才能はこの3つの内どれに当てはまるのか、読み進めていくうちに自身の立ち位置が見えてくると思います。
今後、会社ではどのように仕事を行って行こうかと考えさせられました。
おわりに
登場人物に感情移入しながら読むと、人物の持っている才能が自分の才能に近いかどうかわかり面白いです。
何にでも言えると思うけど、結局は「自分は何者」で、「何がしたい」のか把握することが大事だと思います。
本書を通して自分の才能の片鱗を探す旅をしてみては。

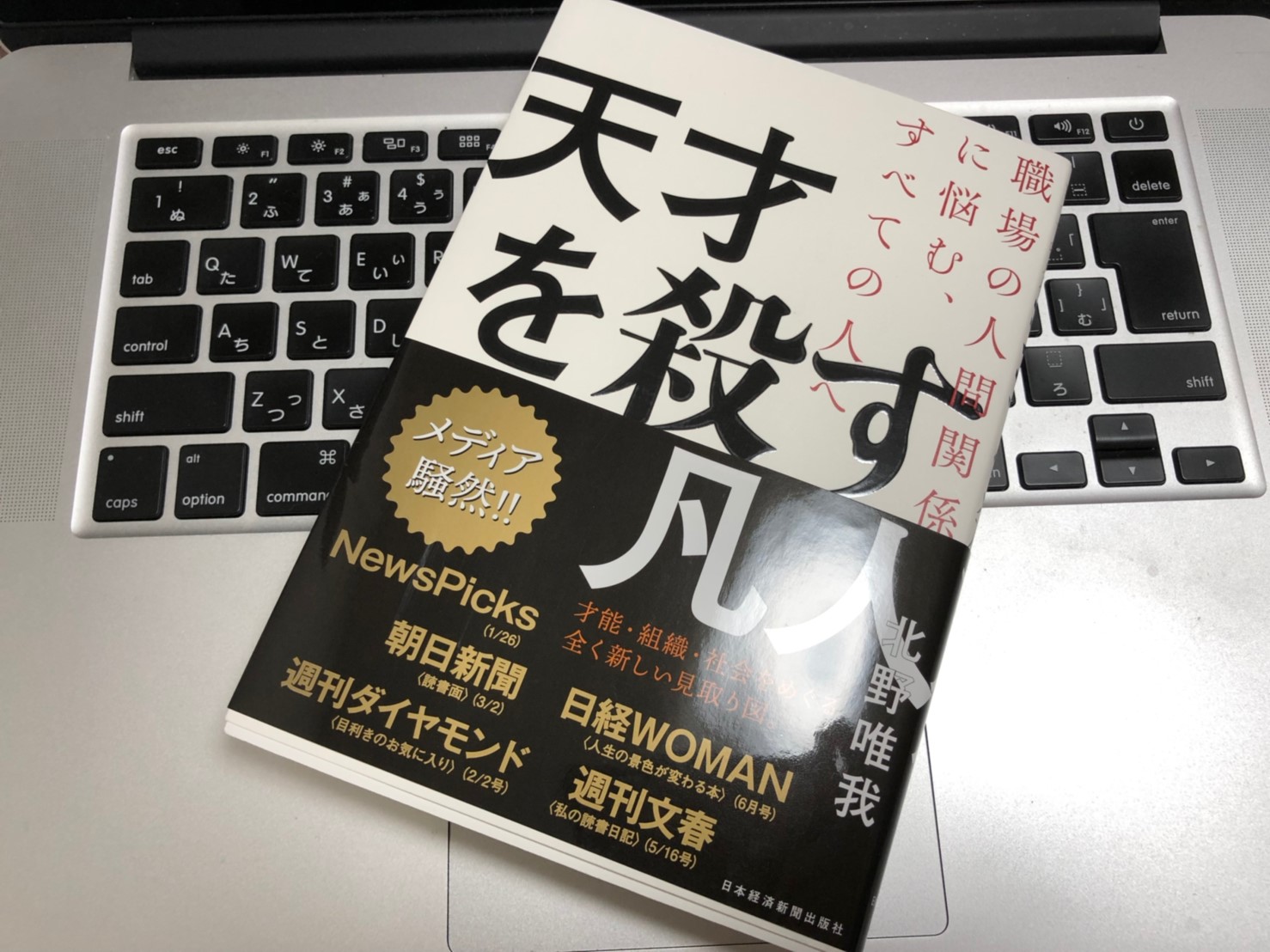

コメント